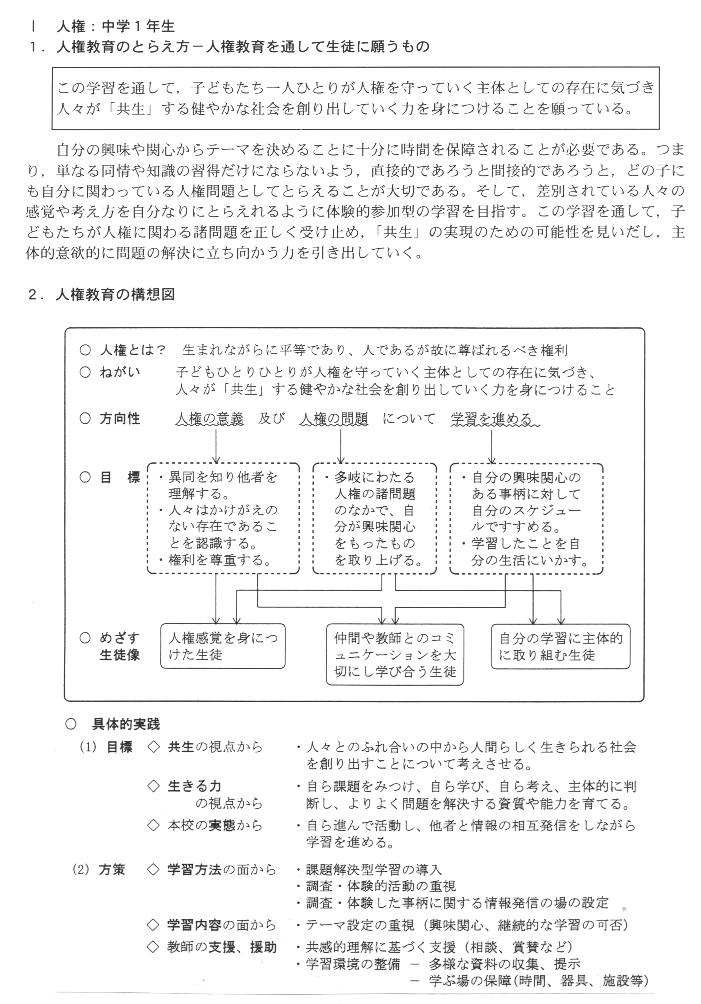 |
| 千葉大学教育学部附属中学校の実践事例 |
| 住 所 | 千葉市稲毛区弥生町1番33号 | 郵便番号 | 263-0022 | ||
| 電 話 | 043-290-2493 | FAX | 043-290-2494 | http://www.jr.chiba-u.ac.jp | |
|
総合的な学習を表すタイトル |
| テーマ別総合学習 |
| キーワード,分類 |
| 横断的,テーマ別総合学習,共生,課題解決型学習,体験的学習,人権教育,国際理解教育,環境教育,T・T |
| 総合的な学習に対する考え方 |
| 自分の身の回りの世界や国際社会の中でおこる事柄を「共生」の視点から見つめ,自分の生き方を考えられる生徒の育成を目指す。また,生徒自身が課題を見つけ,自ら学び,自ら考え,自ら判断し,自ら行動する学習を通して生きる力を身につけられる生徒の育成を目指す。 |
| 総合的な学習の目標(目指すもの) |
| 「共生」の時間は,教師の支援・援助のもと,生徒自らが課題を見つけ,自分の計画に従って追研し,自分なりの解決を図っていく。この時間に取り扱われる課題は,社会的な要請から生じてきた課題,すなわち人権・国際理解・環境の中で生徒自身が取り組みたい課題を「共生」の視点から見つめる。 |
| 総合的な学習の実践形態 |
| 「共生」という視点で生き方を考えられる生徒の育成
Ⅰ 1年(人権) テーマ:いじめ,障害者,民族・人種差別,子どもの権利,福祉,戦争,差別一般,その他。 Ⅱ 2年(国際理解) テーマ:言語,コミュニケ-ション,文化・風習-料理,文化・風習-音楽,文化・風習-スポ-ツ,世界のいろいろ,ボランテイア活動,国際問題。 Ⅲ 3年(環境) テーマ:資源エネルギー,生態,大気,水質・土壌,ゴミ,リサイクル①,リサイクル②,その他。 留意事項 ・テーマは生徒が決定。 ・「共生」の時間は,各教科,「道徳」,特別活動の3領域から,時間を一部出し合って実施。 ・これら3領域を横断的に扱っているというよりは,これら3領域の横に第4領域として設定。 ・第1,第3土曜日の2時間を実施。年間14回の実施予定。 |
| 推進組織 |
| 総合的な学習の各部(人権・国際理解・環境)と運営・調査部会(調査・評価・情報収集)が一体となり,各教科,「道徳」,特別活動の担当者とも連動して取り組んだ。 |
| 文献 |
| 千葉大学教育学部附属中学校研究集録(1997) |
|
コメント(実践から参考になること) |
| 「共生」という一本の柱を中心に据えて,学年ごとで「トピック」総合学習を行っている。生徒は決まった教官のもとで学習するのではなく,それぞれの担当(人権,国際理解,環境ごとに担が決まっている)の教官のところに相談・依頼にいく。全教官が総合学習に関わる。取り扱わている課題が,今日的な社会的要請から生じたものである。 |
| 「共生」の視点をもてる生徒の育成と総合的な学習としての「共生」の時間のカリキュラムの開発と実践が行われた。共生に関しては,特に人権(1年生),国際理解(2年生),環境(3年生)を取り上げ,それぞれ①人権→生まれながらにして平等であり,人であるが故に尊ばれるべき,人と人との共生,②国際理解→同じ人間でありながら規範や制度を異にする文化や社会との共生,③環境→文化や社会の差を超えた人類と自然との共生と捉え,「共生」という一本の柱を通して生き方を考えさせることが追究された。そして,このような内容を扱う学習の場として,特別に総合学習の時間が設置された。 |
総合学習のスタイルは,学年ごとに人権,国際理解,環境という大きなトピックをそれぞれ与え,学年全体で1つのトピックをめぐって学習する「トピック」総合学習に位置する。大きな特徴として,○体験活動の重視,○教師10(11人)が一団となったT・Tによる指導,○生徒自身が課題を決定していけるように,内容にあった導入方法の工夫などが挙げられる。 |
|
1.学習の年間計画(1997年度) |
| 「共生」の時間は,第1,第3土曜日の2時間の実施を基本としている。年間14回実施している。 |
|
回 数 |
月 日 |
曜日 | 時間 |
1年(人権) |
2年(国際理解) |
3年(環境) |
| 第1 回 | 4 月19日 | 土 | 2 |
生徒の実態調査(アンケ-トの実施) |
||
| 第2 回 | 5 月17日 | 土 | 1 |
「共生」の時間の学習全体のガイダンス |
||
| 第3 回 | 5 月31日 | 土 | 2 | 基礎的ガイダンス | 基礎的ガイダンス | 基礎的ガイダンス |
| 第4 回 | 6 月21日 | 土 | 2 | 導入(1)テ-マ決め | 導入(1)テ-マ決め | 導入(1)テ-マ決め |
| 第5 回 | 7 月 5日 | 土 | 2 | 導入(2)テ-マ決め | 導入(2)テ-マ決め | 導入(2)テ-マ決め |
| 第6 回 | 7 月18日 | 金 | 2 | 活動(1) | 活動(1) | 活動(1) |
| 第7 回 | 9 月 6日 | 土 | 2 | 活動(2) | 活動(2) | 活動(2) |
| 第8 回 | 9 月20日 | 土 | 2 | 活動(3)
活動(4) 活動(5) |
活動(3)
活動(4) 活動(5) |
活動(3)
活動(4) 活動(5) |
| 第9 回 | 10月 3日 | 金 | 1~2 | |||
| 第10回 | 10月18日 | 土 | 2 | |||
| 第11回 | 11月15日 | 土 | 2 | 活動(6) | 活動(6) | 活動(6) |
| 第12回 | 1月17日 | 土 | 2 | まとめ(1) | まとめ(1) | まとめ(1) |
| 第13回 | 2月 7日 | 土 | 2 | まとめ(2) | まとめ(2) | |
| 第14回 | 2月21日 | 土 | 2 | 発表 | 発表 | まとめ(2) |
|
*但し,第8回~第10回の活動(3)~(5)は,中間発表会にあてる。 |
|
2.学習方法の特徴 |
| ○ | 学校から外にでて施設などでの見学や調査,学校外施設等での体験活動,大学構内の施設,学校内外での実験や観察,インターネットなどの情報利用,図書やビデオの利用,アンケートの実施,共同研究者との討論など,幅広い学習方法や活動を保障する。 |
| ○ | 決まった場所や決まった教師野本で学習するのではなく,随時,自分が学習したい場所や調査しに行きたい場所,及び調べ方などについて教師と相談しながら学習していく。 |
| ○ | 学習を進めていく上での相談や依頼は,それぞれの担当(人権,国際理解,環境ごとに担当が決まっている)教師のところに行く。 |
| ○ | 自分にとって,調べたいことや途中で考えたことなどの記録を多く残していく。資料コピー,写真(デジタルカメラ),ビデオなども教師と相談して利用していく。 |
| ○ | 学習の途中での発表や最後のまとめについても多様な方法を取り入れる。 |
| ○ | 自分たちの学習のペ-スを基本としながら進めていく。 |
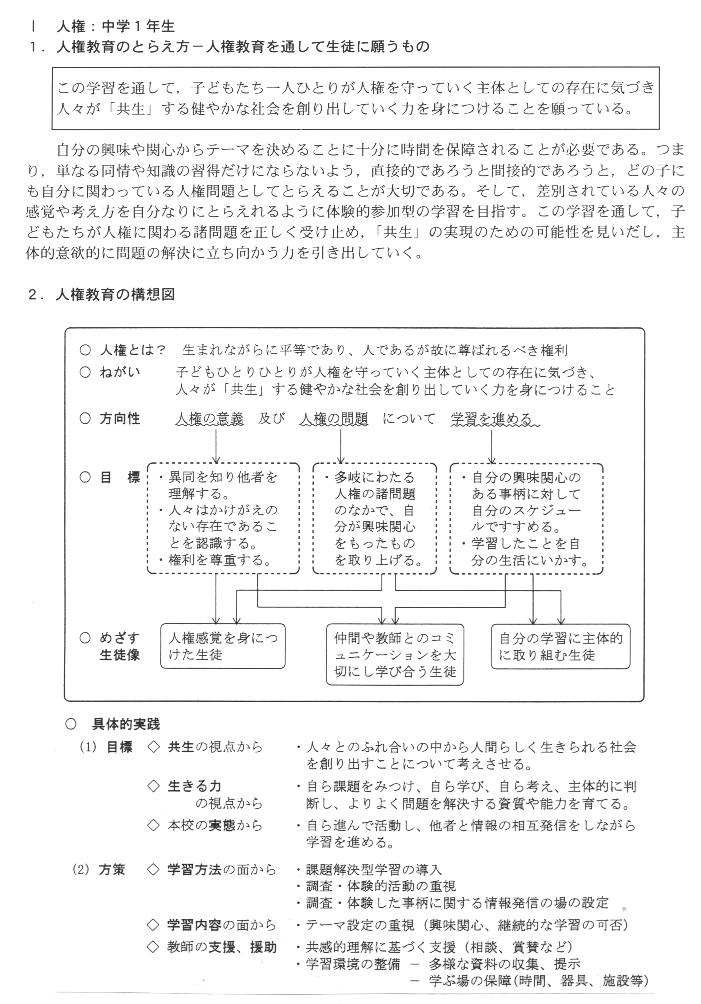 |
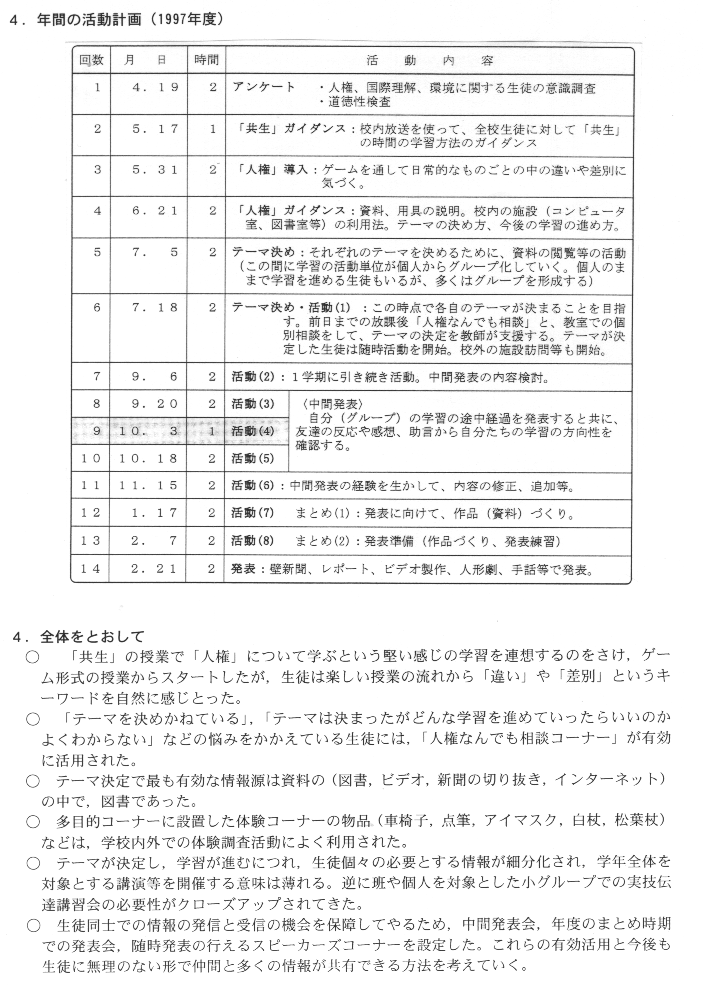 |
 |
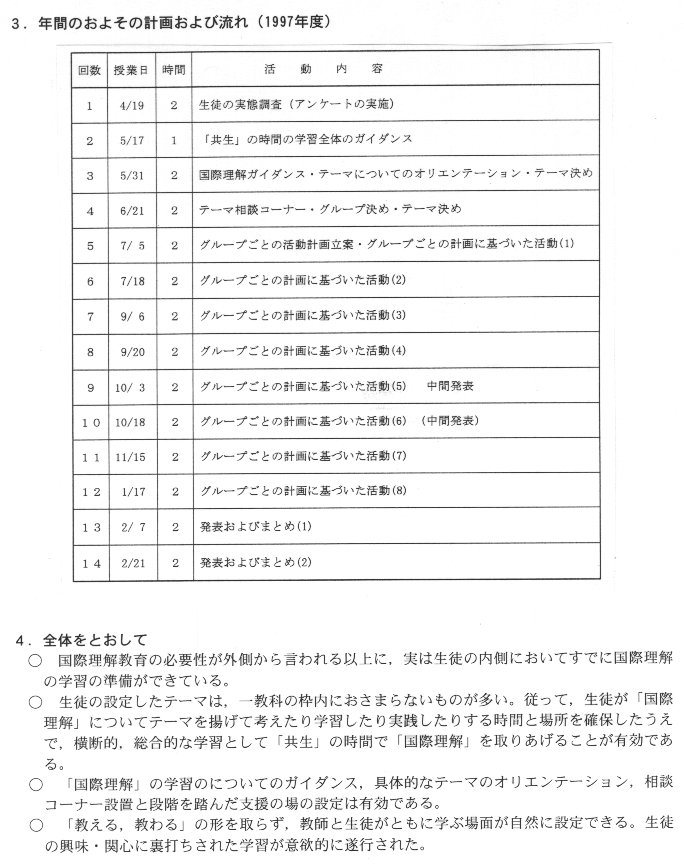 |
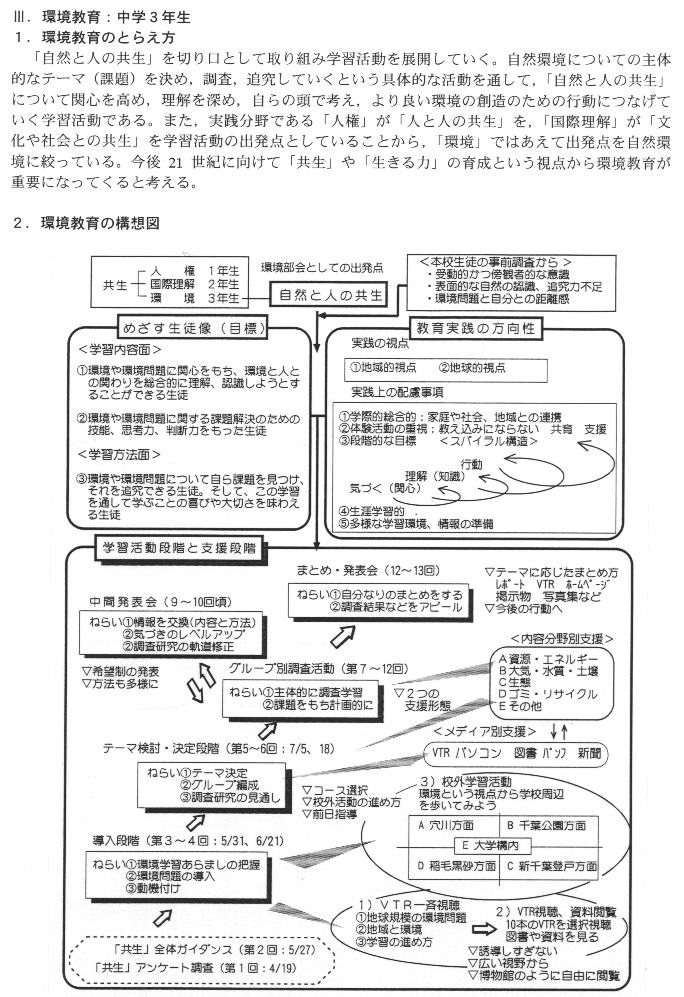 |
 |