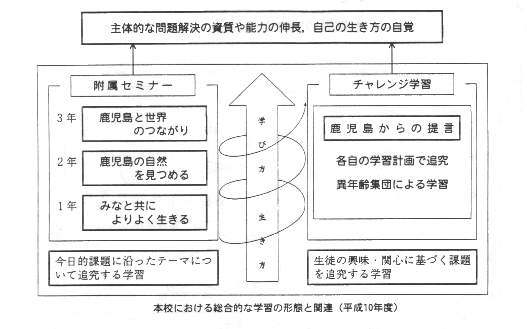 |
| 鹿児島大学教育学附属中学校の実践事例 |
| 住 所 | 鹿児島市郡元一丁目20番35号 | 郵便番号 | 890-0065 | ||
| 電 話 | 099-285-7932 | FAX | 099-285-7950 | ||
|
総合的な学習を表すタイトル |
| 横断的,テーマ別総合学習 |
|
キーワード,分類 |
| 横断的,テーマ別総合学習,体験活動,課題学習,生きる力 |
|
総合的な学習に対する考え方 |
| 「総合的な学習の時間」において,学び合いをいかした学習活動を工夫することによって,自己
肯定感が高まり,他とともによりよく生きる生徒が育成できる。(研究仮説) |
|
総合的な学習の目標(目指すもの) |
| 今日的な課題のテーマを追求する中で,生徒一人一人の課題意識を高め,多様な学び方を学び,自己の生き方を考えさせる(附属セミナー)。生徒一人一人が自己課題を設定し,自分で学習計画を立てて追求する中で,身につけた各自の学び方を生かし,自己の生き方を考えさせる(チャレンジ学習)。 |
|
総合的な学習の実践形態 |
|
推進組織 |
| 教育目標設定部会と総合的な学習推進部会(その下に活動計画作成部会が設置)とで,研究委員会を構成し,総合的な学習の研究に取り組んだ。 |
|
文献 |
| 鹿児島大学教育学部附属中学校−他ととともによりよく生きる生徒を育成する教育課程の編成(1999) |
|
コメント(実践から参考になること) |
| 附属セミナーは,学年ごとにテーマを設定し,課題追求を図る学習を展開する。学年のテーマは現代社会における重要な課題が取り上げられている。自分の学習と生活や社会とのつながりが実感できる体験的な活動が重視されている。チャレンジ学習では,附属セミナーや各教科,特別活動などで身に付いた学び方を生かしながら,問題解決の資質や能力を高めることが期待される。 |
|
「総合的な学習の時間」の学習としての附属セミナーでは,学年ごとに横断的,テーマ別の総合学習を展開することで,「課題の設定方法」や「課題の追究の方法」さらには「課題を表現する方法」といった三つの視点で学び方を発展させている。一方,チャレンジ学習では,学年の枠をこえた,横断的,テーマ別総合学習を展開することで,自分の問題意識に基づいて,自分の身に付けた学び方を実際に生かしながら,試行錯誤を繰り返すことによって,問題解決の資質や能力を高めていく。さらに,その学習が自分のものであるという意識を持たせることによって,未来に向けて自己のあるべき姿や生き方を考えていく。総合的な学習において,「学び合い」を生かした学習活動を工夫し,生徒一人一人の自己肯定感を高め,他とともによりよく生きる生徒の育成を目指した。 |
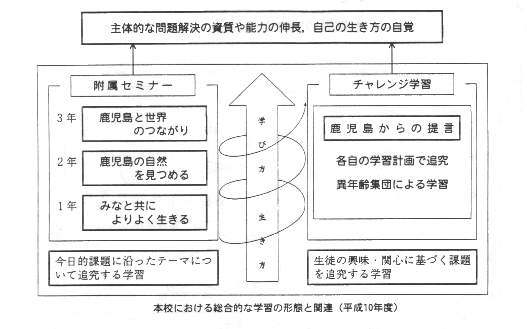 |
|
Ⅰ 総合的な学習の時間における全体活動の流れ |
|
なぜ,そのテーマを自分は学習しているのかとか,なぜ,その課題を自分は追究しているのかを明確にするため,テーマを見つめる段階や課題を見つける段階(導入やオリエンテーション)で,生徒一人一人に自分の学習を他に向かって発信するという意識を持たせる動機づけを行っている。また,課題を調べたり,考えたりする段階では,課題の追究の過程を,定型化した単線型の学習計画ではなく,複数の追究過程や複数の学習コースを設けることで,共通の問題意識や課題を持っている生徒集団の「学び合い」を可能にした。また,学習にリアリテイを持たせるために,学校の持っている特性を生かした体験的な活動を積極的に取り入れている。 |
 |
|
1 附属セミナー(各学年ごとのテーマ別) |
|
各学年ごとに設定されたテーマの学習を通して多様な学び方を身に付けることがねらいである。今日的な課題を取りあげ,人間としての生き方や在り方を真正面から扱うことができ,未来に向けて自己の生き方や在り方を考える上で,とても意味がある。生徒の発信する意識を大切にした学習を行うため,「自ら他にかかわり,自分ができること」という意識を生徒が持てるような活動計画を作成することを重視している。各学年のテーマは「他とのかかわりを広げる」の視点から設定されている。1年生は自分の生きる生活の中における「人とのかかわり」に目を向け,2年生では自己の生活を支えている「自然や環境とのかかわり」に目をむけ,環境問題について考える「鹿児島の自然を見つめて」,3年生ではさらに視野を広げて,自分の生きる社会と「世界の国々・人々とのかかわり」に目を向ける「鹿児島と世界のつながり」と設定してある。 |
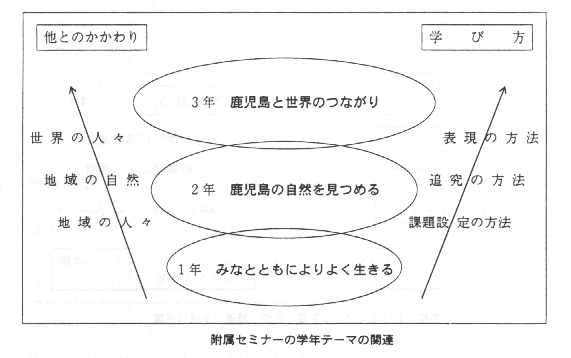 |
|
附属セミナーでは,「課題設定の方法」,「課題の追究方法」,「追究した課題の表現方法」の3つの視点から,各学年の活動計画において,多様な学び方が取り入れられるように工夫されている。 |
|
例えば,附属セミナー「みなとともによりよく生きる」の学習では,1つのテーマに対して複数のコースを設定し,生徒の問題意識に応じてコースを選択させ,多様な追求方法で解決が図れるような工夫がなされている。 |
 |
|
2 チャレンジ学習 |
|
チャレンジ学習では「鹿児島からの提言」という大テーマが設けてある。学習者である生徒一人一人を提言者として位置づけることによって,学習に切実感を持たせてある。提言者として現実社会とのかかわりを持って,「自分でも何かができそうだ」という意識を持たせることができる。また,学習成果を「提言」という形で表現,学習に時間的・空間的な対象の広がりを待たせることができる。生徒は自分が何のために提言するのかという目的,誰に向かって提言するのかという対象,どのような効果的な方法で提言するのかというプレゼンテーションの方法も強く意識できる。そして,「自分の学習である」と実感でき,その結果,自分から他とのかかわりを積極的に持ち,主体的に学習に取り組むことができる。 |
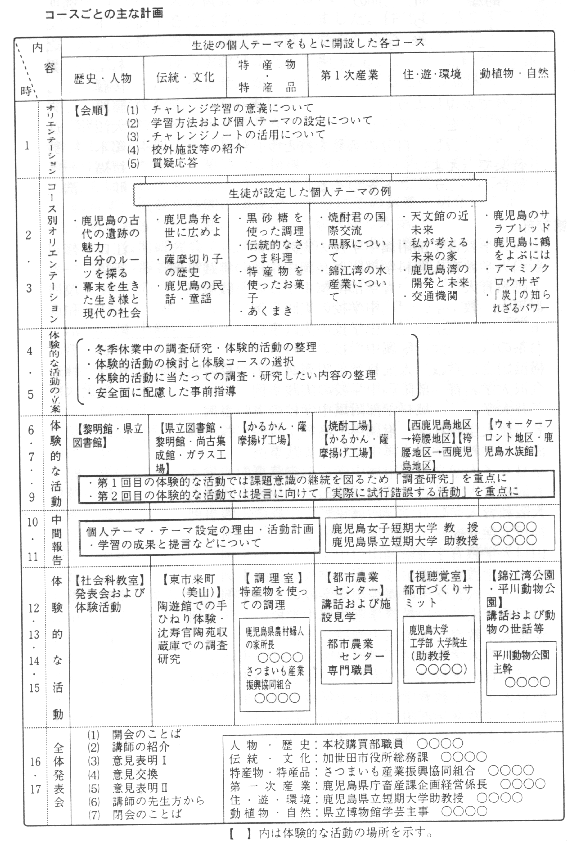 |