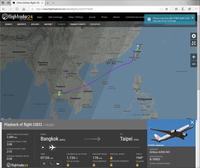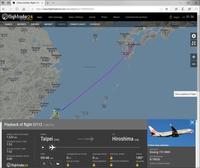内閣府 知財創造教育の普及に向けた地域コンソーシアム(中国)実証授業
2019.02.19


本日7限目に5年生の「提言」選択者を対象に「内閣府 知財創造教育の普及に向けた地域コンソーシアム(中国)」実証授業が行われました。
これは内閣府が進める「知財教育の推進」に基づき、「知財創造教育」は子どもたちに「新しい創造をすること」や「創造されたものを尊重すること」を楽しみながら理解することにより、社会を豊かにしていこうというもので、全国8か所に設置された知財創造教育の普及に向けた地域コンソーシアムが学校で実証授業を行っています。中国地方では山口大学と一般社団法人発明推進協会が担当しており、山口大学知的財産センターの陣内先生とNPO法人日本ダンスうんどう協会の田原先生が来校され、授業を行いました。
陣内先生の軽妙な語りと田原先生のダンスで進行した授業では、知財とは何か、知識の活用、発想についてなど、知財だけに限らず、勉強や研究についても考えることができました。
4年生 英語プレゼンテーションコンテスト
2019.02.14


2/14(木)6時間目のLHRで,4年生の校内英語プレゼンテーションコンテストが行われました。
4年生は2学期のコミュニケーション英語Ⅰの授業でグループプレゼンテーションとディスカッションを統合させた授業に取り組み,クラス予選を勝ち抜いたクラス代表がコンテストで発表を行いました。
どのクラス代表も協力しながら発表を行い,趣向を凝らしたパフォーマンスも見られました。
また,ジャッジ中にはMCの生徒が英語でプレゼンについての感想やコメントをパネルディスカッション風に述べ合うなどして場を盛り上げてくれました。
その後,1位から3位のチームが表彰され,Excellent Speakerも3名選ばれました。努力の成果が実り,笑顔が溢れていました。悔しい思いをした生徒もたくさんいますが,それこそが努力や意欲の表れではないでしょうか。
今回は個人の努力だけではなく,グループでの協働も大事なポイントでした。コンテストを通して,学年全体に学び合いやコミュニケーションが生まれたのではないかと期待しています。





第5回IDEC連携プログラム
2019.01.12


第5回IDEC連携プログラムでは,IDECを訪問し,第3・4回で受けた留学生からの指摘を参考に,加筆・修正をし,発表し,議論しました。最初に,1グループにつき10分間の持ち時間で,5グループが発表を行いました。それぞれ,留学生から発表内容について質問が出て,用語の定義の確認や,統計資料の妥当性について疑義が出ましたが,準備した内容に基づき,発表内容についての理解を深めることができました。プレゼンについて出された留学生からの質問を理解できない時には,IDECの先生方の助けで,質問の意味や意図の確認などが行われる場面もありました。次に,留学生が各自の興味に応じて各グループに分かれ,議論を行いました。その過程では,例えば,自分たちが良いと考えていた解決策は,別の害を生むことがわかったりすることがあったようで,アカデミックな議論の拡がりに終着点を見いだせず,頭を悩ませているグループもありました。しかし総じて,積極的な議論がみられ,考えが深まったようでした。
実施内容の詳細と生徒の感想等は,こちらからご覧ください。
三学期始業式
2019.01.09

三学期の始業式を行いました。
紹介したチームラボの「小人が住まう黒板」は、フジグラン神辺2Fちびっこひろばに設置されています。また、キャナルシティ博多にある未来の遊園地については、こちらをご覧ください。
インフルエンザが流行り始めています。体調を崩さないように、寒い季節を乗り切ってください。
 2019.02.19 17:00
|
2019.02.19 17:00
|